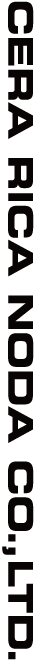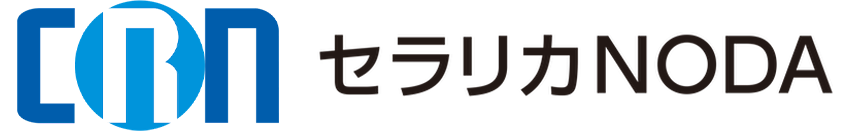「足し算の発想」から「引き算の発想」へ
地球環境問題を最大の契機として、社会は大きな歴史の分岐点に立っています。一言でいえば、合理性や効率性のみを優先してきた、これまでのパラダイムの大転換を迫られていると言うことができます。21世紀に入り、私たちは異質な価値観や発想を受け容れる「寛容さ」や「開かれた態度」、さらには「共通の根」を探求するという新たな姿勢が求められております。この巨大な歴史的転換点にあって、セラリカNODAでは「セラリカ=生命ロウ」という自然の恵みを通して、21世紀にふさわしいパラダイム・チェンジのヒントとなるものをお届けしたいと考えております。
視界に入った「成長の限界」
イギリスの産業革命に始まる近代社会は、物質的な豊かさや快適さと同時に、目に見えない厖大な負債を累積させてきました。すでに1972年には、有名なローマクラブの報告書『成長の限界』により、人類社会のあり方そのものに大きな警鐘が鳴らされました。しかし、環境・資源・貧困・格差・食糧・人口といった課題に対して、本質的な解決は21世紀に至るまで常に先送りされてきました。
パラダイム・チェンジの世紀へ
石油エネルギーをもとにした過剰生産・過剰消費の社会にあって、人類は感謝することを忘れながら巨大な恩恵を享受してきました。拡大しつづける物質的な生産と金融資本主義の発展による富を背景に、人びとは常により便利で快適な生活を求めて、物質的な明るい未来を描き続けてきました。しかし、それによる負債がスウェーデンの少女グレタさんが世界中の指導者や私たち一人一人に示したように、文明社会の存続を根本から脅かすまでにすでに膨らんできています。社会は近代以降の自らのあり方を根本から問い直す分岐点にまさに立たされています。
環境破壊と人間の理性の限界
自然やモノを無数の要素の集合として考え、要素間の関係や法則性を探求することで世界のすべてを捉えることができるとするのが現代の「機械論的な考え方」です。ここには、大いなる神のような存在が不在の中で人間の理性や思考に対する過剰な自信があります。この人間への過剰な自信が科学の発展や現代文明の繁栄をもたらしたことは確かです。ですが、同時に後戻り出来ないほど環境や真心を破壊し尽くしてきたのも同じ事が原因でした。
「科学万能・効率優先」の世界観
人間にとっての利用可能性の側面からだけ世界をみると、環境をつくる自然やモノは、化学記号で表されるような単なる物理的存在にすぎません。自然やモノは細かく要素に分割されて、いつでもつくったり、取り替えたりできる機械の部品と同じものになってしまいました。ここに近代社会を推進した科学万能・効率優先の人間中心の「機械論的パラダイム」がありました。
数値化される「足し算」の思想
市場や経済の世界を支配してきたのは、豊かさは「数値」や「量」に変換できるという論理でした。そして、貨幣価値に変換された人間の富は、「足し算」されればされるほど大量になり、比較され、量そのものがいつの間にか価値を持つことになります。しかし、「足し算」の論理では捉えられない価値もあります。その典型が、「自然」や「生命」です。
分割できない「自然」と「生命」
自然や生命、そして地球全体は、一つの生態系として動的な秩序や調和を保っています。そこには何一つ要素に分割できるような境界線は存在しません。部分は全体と切れ目なくつながり、全体は部分の働きと同時に存在しています。
「モノは単なるモノではない」
効率性を最優先する近代西欧的な思考は、「数値」や「量」では表せない、歴史的に積み重なっていく無形の「関係」というものに目を向けることが苦手です。人と人、人と自然、人とモノ。そうした様々な関係の間には、人びとの慎ましい営みの記憶や想い、乏しいからこそ起こるモノや自然に対する感謝の念と生きる工夫。そのような奥深い想いや知恵が折り畳まれています。そこにこそ、セラリカNODAの「生きものは、ものであっても単なるものではない」という思想の根につながっていくものがあります。
「引き算」の思想を再発見する
日本には古くから、「足し算」の発想とはまったく異なる文化が滔々と流れてきました。例えば、それは「茶の湯」「水墨画」「枯山水」「短歌」などの世界に見ることができます。大切な何かを伝えるために、過剰な演出や装飾を排して、あえて「引き算」する。そこには、「足し算」の豊かさでは到達できない、歴史的に培われた日本独自の「コスモロジー(世界観)」があります。
日本文化の可能性を生かす
大量生産・大量消費の生み出す快楽には限界があります。いくら豪奢に生活や自分を飾り立てても、それだけでは美や価値に至ることはできません。例えば、「恥らい」「はにかみ」「幽玄」「無常」を主題とした日本人の感性は、「足し算」というより、むしろ「引き算」を突き詰めた表現の中に、その本質を見出すことができます。日本人は本来、無形の美しさや奥深さを享受する感性を持っていたのだとも言うことができます。21世紀に至り、そうした日本的美意識はますます重要になってきました。
石油文明と重化学工業の黄金期
戦後の日本は、アメリカ流の「科学技術万能・効率スピード優先」のパラダイムに従うことで、現代の繁栄を築き上げました。そこには焼け野原からの何としてもの復興とアメリカの物に溢れた豊かな生活を憧れのモデルにした目に見える豊かさの実現へ向かうという、三丁目の夕日的な国民共通のテーマがありました。当時、アメリカはいわば石油文明のチャンピオンとしてすでに黄金期を迎えていました。ハリウッド映画やキャデラックなど、当時のアメリカ文化は豊かさのシンボルとして日本人を魅了していきました。
石油文明のチャンピオンの敗北
日本が高度成長のピークを迎えていた1970年代、アメリカでは時代の大転換が始まりました。最大の分岐点は、1975年のベトナム戦争です。第二次世界大戦で世界中で使われた爆弾よりも多くを小さなベトナムに落としたにも関わらずの思わぬ敗北でした。この敗北は「アメリカの正義」、すなわち石油文明の繁栄を謳歌してきたアメリカの自信や正当性を根底から揺るがす歴史的大事件でもありました。アジアの小国ベトナムは、なぜ超大国アメリカに勝利できたのでしょうか。
ベトナムの強さの源にあるもの
広島大学総合科学部元教授 芝田進午によれば、ベトナム文化の根底には、ラグビーワールドカップで有名になった「一人は万民のために。万民は一人のために」(One for All, All for One.)の思想があるといいます。全体(国家)と部分(個人)が切れ目なくつながっているという意味で、一つの生命としてのベトナム民族と言い換えることもできます。そこにベトナム国民の誇りと強さの源泉を発見したのです。
相手を認める「寛容」と「開かれた態度」
さらに、ベトナム文化の特筆すべき性格として、「寛容の精神」「開かれた態度」を指摘しています。共産主義最大の問題は、歴史の中で独裁者が政敵を100万、1000万人単位で粛清し、虐殺してきたことです。人間の原罪とも言える根本的弱点とも言えます。この困難克服に向けて、例えば、人を「批判」する場合でも、相手の良いところはそのまま認めながら、相手の本質を深く研究することで、より正確な表現に訂正し再構成して提示します。教条主義的に頭から決めつけたり、批判を人格否定まですぐにエスカレートしたり粛正したりすることがなく、どこまでも相手の本質を尊重する。そうした独自の作法や哲学が、ベトナム人の強靭さの背景にありました。
「原理主義」「二元論」から「多様性の包摂」へ
生物の世界では、環境変化にうまく適応できないものは最初に淘汰されていきます。人間の世界でも、自由民主主義のトランプのアメリカにおいても原理主義的に自らの「正しさ」に固執し、一方では異質なものを「悪」として切り捨てる「善悪二元論的な態度」に終始すれば、国ははっきりと2つに分裂し、誇るべきアメリカの多様性を認める文化はどんどんやせ細っていきます。逆に、ベトナムの人びとが示すような「寛容」や「多様性に開かれた態度」は、生産的なコミュニケーションや学びの回路を開き、違いがある事がダイバーシティーとして逆に豊かで力強い文化を育んでいくことになります。
物質的な豊かさでは測れない豊かさがある
アジアの様々な国の人たちとじっくり話し合うと、物質的な豊かさとは別の、もっと生活に根ざした深い豊かさがあることに気づかされます。それは、「善か悪か」「敵か味方か」「1かゼロか」といった単純な図式で物事を割り切ってしまう現代社会の頭脳中心のスピード感覚では決して巡り会う事のないような不思議な豊かさです。アジアの国々には、経済的な指標やデータに一喜一憂しない、そのぬかるみが生み出す明るさとエネルギーに溢れています。その背景には、何が本当の豊かさであり、自分たちが何を一番大切にすべきかを、自然と共生する長い困難の歴史の中で育んできた奥深い英知に見ることができます
セラリカと真の豊かな21世紀へ
経済的には貧しくとも根底にある眼差しの豊かなアジアの民衆の中にある、多様な人間のあり方に開かれ、自然や生命に開かれ、すべてを包摂するような豊かさに出会うためには、何らかの導きの糸が必要です。何千万年・何億年という生命の営みが生み出した「セラリカ=生命ロウ」には、そうした導きの糸となる汲み尽せない知恵や価値が秘められています。生きとし生けるものそれぞれの多様性を生かし「共生」を目指すべき時代のなかで、これからもセラリカNODAは「セラリカ=生命ロウ」の可能性を深く追求して参ります。